
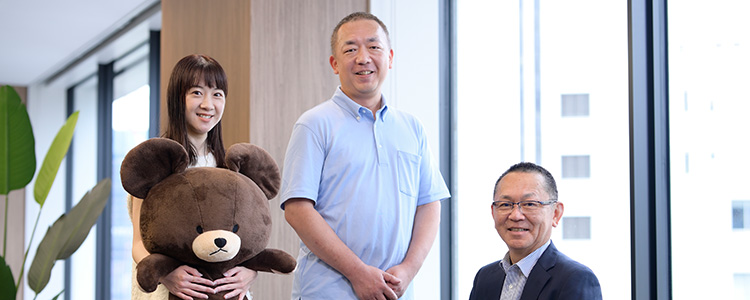
 サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み
事業と一体の取り組みを通じて
持続可能な社会づくりに貢献
バンダイナムコのサステナブル活動は大きく進展しました。
チーフサステナビリティオフィサー(CSO)とともに、
一連の取り組みをリードする推進室のメンバー2人に、
この2年間の総括や目指す将来像を聞きました。
経営企画本部
サステナビリティ推進室
サステナビリティ推進チーム
経営企画本部
サステナビリティ推進室
ゼネラルマネージャー
取締役
チーフサステナビリティオフィサー(CSO)
 サステナビリティ意識の向上と環境整備
サステナビリティ意識の向上と環境整備

浅古:この2年間、WEB社内報や従業員向けのイベント「サステナビリティWEEK」など従業員に向けた様々な仕掛けによって環境整備を進めた結果、“事業プラスアルファ”ではない、「事業を通じたサステナブル活動」の考え方が浸透してきました。対外的な情報発信についても改善を続け、まだ足りない部分はありますがメディアや第三者機関から一定の評価が得られるようになりました。グループサステナビリティ委員会における討議も、課題の優先順位を意識し、より具体的な議論になってきたと思います。
小林(聡):私はこの春、着任したばかりですが、2024年3月期は、一連の環境整備の効果で、活動が一気に具体化した1年だと感じています。サステナブル活動には前任の頃より携わっていましたが、会社や部署間の交流が行われることで、問題意識の共有・浸透につながっていると思います。
小林(り):私は推進室の発足時から在籍し、WEB社内報の制作を中心に様々な業務を担当しています。グループ内の意識の変化、自分事化は、エンゲージメントサーベイの結果に表れていますし、日々の業務でも実感します。国内外のグループ会社が取り組むサステナブル活動情報が自然に集まってくるようになったことも、その一例です。
 グローバルの「サミット」開催
グローバルの「サミット」開催
浅古:時代とともに企業への社会的要請も高まり、求められる在り方も変化しています。こうした状況を踏まえ、グループ全体で意思統一と横の情報共有や連携をはかるべく、2023年10月に第1回「グローバルサステナビリティサミット」を開催しました。海外の地域統括会社と国内の事業統括会社の担当者が一堂に会し、幅広いテーマで2日間にわたり議論しました。
小林(聡):サミットでは、国内外での取り組み内容の説明や、活動に向けた考え方の統一をはかりました。次回は2025年開催を予定していますが、グループとしてのロードマップ、特に各バリューチェーンにおけるサステナビリティ戦略を構築していくことが課題になります。
小林(り):担当者と直接会って話せたことで、その後のコミュニケーションがスムーズになりました。初めての試みとして、大きな意義があったと思います。
 環境課題への対応強化
環境課題への対応強化
浅古:2050年のCO2排出実質ゼロという目標に向け、取り組みを進めています。もっとも、これはScope1/2の話で、Scope3については状況を精査している段階です。また削減手法としては、排出量の削減に加え、カーボンクレジットの活用なども検討しています。なお、2023年9月にはTCFD提言への賛同を表明し、簡易なシナリオ分析も実施しました。プラスチック廃棄物の削減については、できるだけ早期に具体的な施策を推進するため検討を進めています。
小林(聡):私たちはサステナブル活動を「IP軸戦略のもと、ファンなどすべてのステークホルダーとともにサステナビリティを推進する活動」と位置付けています。例えば「ガンプラリサイクルプロジェクト」のように、様々なIPの力を活用しつつ、ファンとともにバンダイナムコらしい活動を展開していくのが、目指す形です。

 マテリアリティとしての人権
マテリアリティとしての人権
浅古:私たちは早くから人権課題に向き合ってきました。2023年11月に策定した「バンダイナムコグループ人権方針」は、社内に存在していた各種規定や考えを統一・体系化したものであり、今後仕組みを具体化していく「人権デューディリジェンス」(詳しくはP.88をご覧ください)も従来実施しているトイホビー事業におけるCoC(Code of Conduct:行動規範)監査の発展形です。現時点で主要な事業会社におけるモニタリングは一通り実施しています。今後は、各国法令に対応した措置も含め、幅広く取り組んでいきたいと思います。
小林(り):サステナビリティというとエコのイメージが強いのか、マテリアリティの1つ「尊重しあえる職場環境の実現」に「人権」が含まれるという認識は、まだ社内に定着していないようです。分かりやすい伝え方を考えていくのも、推進室の仕事ではないかと感じます。
小林(聡):マテリアリティの文言からイメージしやすい活動とイメージしづらい活動があって、前者の浸透が進む一方、後者の存在が見えにくくなっていることは確かです。現場の実情を踏まえて問題点を整理し、必要に応じて表現方法の変更も検討していきたいと思います。
 コンプライアンスの徹底に向けて
コンプライアンスの徹底に向けて
浅古:2023年に開示した複数のコンプライアンス事案についてはステークホルダーの皆様にご心配をおかけしました。業務のリモート化が進んだことなどにより、業務の属人化や牽制が利きづらい状況となったことが原因だと考えています。これは元をただせば、平時の体制や意識の問題です。業務プロセスの徹底的な見直しにより再発防止に努めるとともに、今まで以上にコンプライアンス意識の向上に努めていきます。
小林(聡):グループの規模が拡大し、事業内容や人員構成も多様化する中、潜在的リスクは常にあると認識しています。e-Learningや研修など様々な機会を通じ、バンダイナムコの考え方を従業員一人ひとりに繰り返し伝えていきます。
 バンダイナムコらしいサステナブル活動へ
バンダイナムコらしいサステナブル活動へ
浅古:どのような方針や施策であっても、それを形にしていくのは従業員一人ひとりです。従業員が腹落ちできないような施策は、実効性に欠けるものとなります。「バンダイナムコらしさ」をどう進化させていくかという視点を常に忘れず、様々な課題に向き合っていきます。
小林(聡):ガンプラリサイクルプロジェクトや低消費電力を実現したクレーンゲーム機「CLENA3」のように、事業に即した様々な先進的取り組みが生まれています。従業員やファンの皆様とともに、IPの力や技術力を駆使したサステナブル活動を推進していきたいと思います。

小林(り):エンターテインメント企業らしく、サステナビリティを身近に楽しく感じられ、ワクワクしながら参加できるイベント、施策をつくりあげていきたいと思います。そのためにも私自身、ワクワクする気持ちを大切に、日々の業務に取り組んでいきます。


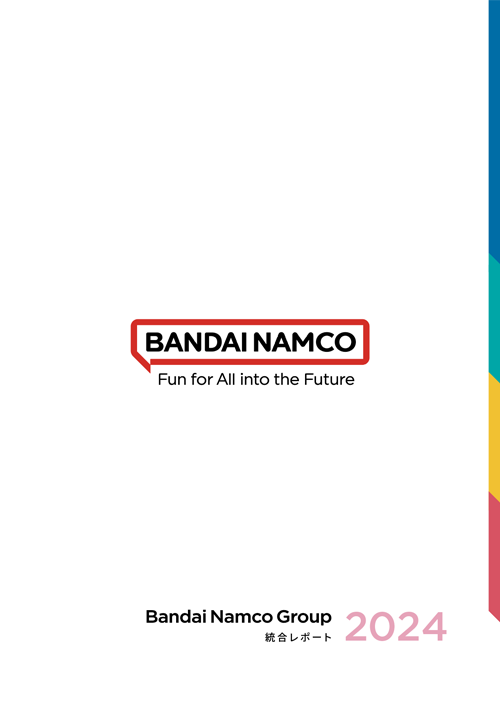
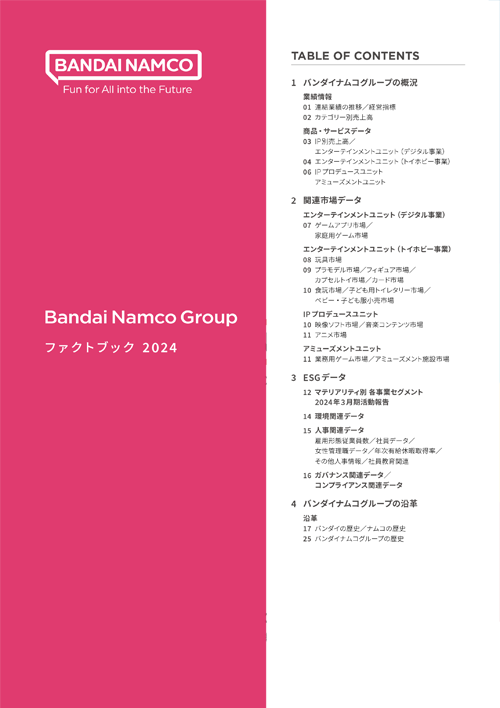

 MESSAGE
MESSAGE 統合レポート(日本語版)
統合レポート(日本語版) 10.5 MB
10.5 MB 多彩な事業領域
多彩な事業領域