

 社外取締役座談会
社外取締役座談会
企業価値の持続的拡大に邁進していきます。
デジタル事業の損失計上など一部に課題を残す結果となりました。
グループの現状について、当社社外取締役5名が財務・非財務両面で意見交換しました。
 島田 俊夫
社外取締役
島田 俊夫
社外取締役
 川名 浩一
社外取締役
川名 浩一
社外取締役
 篠田 徹
社外取締役 監査等委員
篠田 徹
社外取締役 監査等委員
 桑原 聡子
社外取締役 監査等委員
桑原 聡子
社外取締役 監査等委員
 小宮 孝之
社外取締役 監査等委員
小宮 孝之
社外取締役 監査等委員
 機関設計変更2年を振り返って
機関設計変更2年を振り返って
島田:監査等委員会設置会社への移行(2022年)から2年が経過しました。この間のガバナンス改革を振り返ると、取締役会への上程議案の絞り込み、審議議案と報告議案の区分けなど、モニタリングボードへの進化は着実に進んでいます。一方で、モニタリングの実効性をより高めていくためには、与えられた個別テーマの議論を超え、継続的な「常時モニタリング」を実現する必要があります。今後パーパスと個別テーマをつなぐ中長期的視点の共有、適切なアジェンダ設定などについて、議論を深めていきたいと考えています。
桑原:移行1年目は、従来のマネジメントボード的発想が残っていたのが、ここへきて、取締役会の役割やモニタリングの在り方、「何を、いつ、どこで論じるか」というアジェンダ設定の問題が焦点になる、新たなステージに入ってきました。グローバル化が進む中でのグループガバナンスの在り方についても、今後さらに議論を深めていく必要があります。
川名:取締役会の空気が変わってきたのは、従来の監査役と異なり議決権を持つ取締役監査等委員の参画が大きいと思います。加えて、監査等委員会の議論内容がスムーズに共有されるようになったこと、常勤役員会と取締役会の役割分担がより明確になってきたことも重要です。
篠田:一般にグループ全体の監査は、持株会社の役員だけでできるものではありません。私たち持株会社の監査等委員、各事業統括会社の監査役、その傘下にある事業会社の監査役、さらには各社の内部監査部門まで、広範な協力・連携体制が必要です。2年前、事業統括会社を介した情報共有スキームが強化されたことも、ガバナンスの進化に大きく寄与しています。
小宮:私自身、事業統括会社の監査役を務めていた頃と比較すると、議決権があるかないかで、取締役会に臨む際の緊張感が違ってきます。また、発言者が増えたことで、多様な視点からの検討がなされていると感じます。
 取締役会での主な提言・活動内容
取締役会での主な提言・活動内容
小宮:2024年3月期(以下、当期)は、デジタル事業で相当額の評価損・処分損計上がありましたが、これは以前から課題としてきた部分です。現状では業績の拡大で損失分を吸収できているとはいえ、リスクの極小化に向けた取り組みを今後とも注視していきます。
篠田:一部の海外の事業会社では、管理部門にやや脆弱な部分が以前から見受けられました。こうした会社は比較的規模が小さくリソースも限られるため、地域統括会社や国内のグループ管理本部が連携してリーダーシップを発揮しサポートすることが大切です。海外展開の拡大に伴い管理面も重要なファクターになることを、常々強調しています。
川名:ゲームの開発規模が巨大化する中、より効率的なプロジェクトマネジメントに向け、リソースの最適化やプロセスの可視化などのエンジニアリングの手法が参考になると見ています。またグローバル化との関連では、権限と責任の整合性、国内外の人材育成などを重視し、多角的な提言を行っています。
桑原:当期は残念ながら大きなコンプライアンス事案があったことから、監査等委員会として提言を行いました。またデジタル事業の損失については、グループ全体では好業績が続く中、持株会社の取締役会から見えづらい問題もあることを感じました。この反省を踏まえつつ、事業統括会社における今後の対応を精査しサポートしていきます。
島田:取締役会のさらなる進化に向けた仕掛けとして、実効性評価の質問票を見直し、資本収益性など様々な質問項目を網羅しました。コーポレートガバナンス・コードの改訂動向も踏まえ、全員の意識を高めていく機会になったと思います。また、先ほどの常時モニタリングの問題に関係しますが、特に情報セキュリティや内部統制といった、日々の継続的取り組みが物を言うテーマは、取締役会の議題に上りづらいものです。折に触れ他の議題に沿いながら、執行側の注意喚起に努めています。
 コンプライアンスの徹底に向けて
コンプライアンスの徹底に向けて
桑原:今回のコンプライアンス事案について、監査等委員会では、事案発覚の報告を受けて以降、その後の事態の推移や原因究明・再発防止の状況についても随時、確認を行いました。執行側の事後的対応は概ね妥当と考えておりますが、原因究明・再発防止の徹底とともに、グループ全体の意識向上に向けたトップメッセージの発信もお願いしました。今後も定期的に、取り組み状況を確認していきます。
島田:万単位の人々の日々の行動を完全に律することは難しく、むしろ不正を起こさせない、あるいは起こしにくい仕組みづくりが重要です。例えば、現金の取り扱いの制限や、ITを活用した複数決裁者の承認義務付けなどが考えられます。それをどこまで徹底すべきかは、生産性との兼ね合いであり、最終的には事業会社のカルチャーの問題になるでしょう。
川名:仕組み・文化・リーダーシップの3軸からのアプローチが重要です。まず仕組みに関しては、組織内に光の当たらない“暗がり”をつくらないこと。文化に関しては、世界に笑顔と幸せを送り届ける一員としての自覚を、一人ひとりに促すこと。そして様々な組織の責任者が、コンプライアンスの浸透・定着に向けリーダーシップを発揮することです。

中長期的視点の共有、適切な
アジェンダ設定などについて、
議論を深めていきたいと考えています。
 2024年3月期の業績評価
2024年3月期の業績評価
川名:当期は、これまで業績を牽引したデジタル事業が足踏みした一方で、トイホビー事業、アミューズメント事業が過去最高業績を記録しました。幅広い事業間の「相互補完」が、グループ業績の安定的向上をもたらしています。現在さらに、各事業間の積極的な「相乗効果」を創出する、新たな取り組みが始まっています。ファンの想像を超えたチャレンジが、様々な分野に波及していく展開を期待しています。
篠田:売上高が当期初めて1兆円を突破、営業利益も減益とはいえまずまずの成績です。他方、デジタル事業は、かなりの損失を計上しました。背景として、ユーザーニーズの多様化、開発期間の長期化・コスト増といった要因があり、同様の状況は競合他社でも生じています。抜本的な開発体制見直しが効果を発揮するには、しばらく時間がかかると見ています。
島田:アウトプットの数字だけでなく、事業ごとの業績の内訳まで厳しくチェックする必要があるな、と感じました。特に業績予想の下方修正があったことを、重く受け止めています。当社に先を見通す力が足りていなかったというのは、投資家の方々の期待を結果的に裏切ったことになります。そうした期待に常に応えられるわけではないものの、可能な限りの努力をする責任があるはずです。
 次期中期計画と長期ビジョンに向けて
次期中期計画と長期ビジョンに向けて
島田:当社グループでは現状、長期ビジョンの公表を行っていません。中期計画を立てる際、前の中期計画に新しいものを継ぎ足すより、長期視点でのありたい姿からバックキャストするやり方のほうが、投資家の方々の理解も得やすいでしょう。業界特有の環境変化の速さに留意する必要はあるものの、検討する価値はあるように思います。
桑原:私が社外取締役に就任した2017年3月期から役員合宿がスタートし、その第1回のテーマが「10年後のありたい姿」で、社内的には数値目標の設定もありました。今、同種のものをつくるとすれば、おそらくサステナビリティ課題をより深く掘り下げたビジョンになるでしょう。次期中期計画策定の議論も、そうした将来像を意識したものになると思います。
篠田:Vision Meetingでも発言がありましたが、成長機会を海外に求めるのであれば、それに対応した新たなグローバル人材戦略が必要です。事業基盤を支えるコーポレート人材に加え、IPの獲得・創出に当たる人材の確保・育成方針は、中期計画ないし長期ビジョンの中で詰めていく必要があるでしょう。
小宮:各事業会社が立てた目標を積み上げるやり方は、それはそれで合理的だと思います。ただ、ある種の成長投資に関しては、グループ主導のアプローチが有効ですし、現在それが可能な状況にあると見ています。
川名:バンダイナムコのようにファンに世界観を提示するビジネスの場合、何をするか(what)ということは、基本的にはファンと向き合う現場の人々が決めることでしょう。ただ、そのwhatの部分が固まれば、それをいかに実現するか(how)は、私たちの吟味の対象となります。様々な助言や疑問を提供し、実現プロセスに参画していきたいと思います。
 成長に向け対処すべきリスク
成長に向け対処すべきリスク
小宮:デジタル事業は、ボリュームが大きいだけに、チャンスとリスクがともに存在します。リスクとは、開発期間の長期化により、外部環境の変化に長くさらされ、また投資額も膨らむことです。リスク最小化とリターン最大化の間で、適切なバランスが求められるでしょう。
篠田:グローバル展開が加速する中、海外事業のガバナンス構築は喫緊の課題です。事業の拡大と管理体制の整備は車の両輪であり、後者にはコーポレート人材の確保・育成・配置が含まれます。こうした取り組みの立ち遅れが、最大のリスクになると考えています。
島田:私が考える最大のリスクは、技術革新あるいは生活スタイルの変化がもたらすゲームチェンジです。技術革新の代表例が、AIの進展で、生活スタイルの変化においては、極端に“タイパ”を重視する若者世代の消費行動などが挙げられます。こうした変化が実際にどれほどのインパクトを持つのか、あるいはゲームチェンジが近々起こり得るのかについては、現状よく分かりません。ただ、こうした理論的な可能性を常に意識しておく必要はあるように思います。
こうした要素を適切にコントロールすることが、企業として勝ち残る条件になっていくでしょう。

桑原:短期的な課題・リスクとしては、グローバルのグループガバナンスと、ゲーム開発体制見直しの2つを想定しています。長期的には、少子化やメディア視聴環境の変化が進む中、次世代のファン育成が大きな課題になっていくでしょう。
川名:事業領域の拡大、ビジネスモデルの複雑化に伴い、コンフリクトの増大が予想されます。例えばAIの導入は、省力化・生産性向上と、人間的な創造性の対立関係をもたらすでしょう。また、当社グループと様々なパートナーの間には、部分的な利害の不一致も生じ得ます。海外ビジネスにおいては、現地の倫理・宗教観との衝突も想定されます。こうした要素を適切にコントロールすることが、企業として勝ち残る条件になっていくでしょう。
 多面的なダイバーシティ推進へ
多面的なダイバーシティ推進へ
桑原:2023年、持株会社で女性初の社内取締役である宇田川取締役が就任しました。各社では、さらに女性の登用が進んでいます。とはいえ、国内主要グループ会社の女性管理職比率はまだ3割に満たず、引き続き努力が必要です。ジェンダー以外のダイバーシティとしては、真のグローバル化に向け、各地域のグループ会社における現地人材のマネジメント層への登用の増加、その先の外国籍の取締役誕生に期待しています。

川名:女性活躍については、人事報酬委員会でもよく議題に上がっています。宇田川取締役というロールモデルがあり、さらに下の世代には優秀な方が数多くおられるので、女性比率の向上は時間の問題と見ています。今後は徐々に「認知的ダイバーシティ」、つまり経験・知見・考え方の多様性が焦点になっていくでしょう。ジェンダーや国籍を問わず、優秀な人材を発掘・育成し、権限と責任、活躍する場を与えていくことが重要です。
島田:今のお話に付け加えれば、障がい者雇用の問題が挙げられます。日本の人口に占める障がい者比率が9.2%*1である以上、法定雇用率*2を優に上回る雇用があってしかるべきです。時価総額で国内トップ100に入る会社には、相応の社会的責任が求められるからです。障がい者にとどまらず、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の深化については、多角的な視点の取り組みが必要と考えています。
*1 2023年度 障害者白書より
*2 2025年3月期に従来の2.3%から2.5%、さらに2027年3月期には2.7%へ引き上げられる。
篠田:障がい者雇用率の抜本的引き上げには、特例子会社だけでなく、各社が雇用の受け皿となることが必要です。現在、一部のアミューズメント施設での障がい者雇用が始まっています。他の地域・事業会社でも、こうした取り組みを進めてほしいと思います。
小宮:アミューズメント施設の場合、近年の人手不足という課題も抱えています。いずれにせよ、これを機に、障がい者を含む多様な人材の活用を強化していくべきでしょう。
 人事報酬委員会における取り組み
人事報酬委員会における取り組み
島田:2022年の役員報酬体系見直しで、サステナビリティ評価が導入されました。脱炭素や従業員エンゲージメントなどに関するKPIを設定し、その達成度を取締役(監査等委員および社外取締役を除く)報酬に反映させるものです。1年目(2023年3月期)は制度の導入にとどまりましたが、2年目の当期は、より実質的な運用に向け、評価スコアをニュートラルから1段階引き上げました。今後はさらにKPIそのものの見直し・拡充を検討していきます。
川名:サステナビリティ評価で設定された指標のうち、脱炭素のKPIは達成されており、またガンプラリサイクルプロジェクトなど、注目すべき取り組みもなされています。人事報酬委員会として今回、評価すべきものは評価する姿勢を明確にしたものです。
桑原:サステナビリティ評価については、導入そのものが大きなインパクトを与えたはずです。他方、運用面ではいくつか課題があります。まず、KPIが達成されたのに正当な評価がないようでは、十分な動機付けになりません。また、KPIがあまりに達成困難だと、評価スコアが弾力的に変動できません。他社動向も参考に見直しを進め、より良い指標につくり込んでいきたいと思います。
島田:また、人事報酬委員会では、経営人材育成の議論を進めています。リーダーに求められる様々な経験・資質を抽出し、その成果は実際の役員人事にも活かされています。従来は、次世代の人材を後継者候補としていましたが、今回さらに、次々世代も候補に含めました。柔軟かつ思い切った人材登用ができるよう、対象世代に幅を持たせるのが目的です。

 グループのさらなる成長に向けて
グループのさらなる成長に向けて
島田:これからは、社外取締役の存在意義が改めて問い直される時代になるでしょう。私たちはビジネスの現場や、世の中の動きを熟知し、両者の橋渡しをしなければなりません。投資家の皆様と対話する姿勢を忘れず、外部の視点から経営の客観性を高めるべく、今後とも研鑽を重ねてまいります。
桑原:進行中の2025年3月期は、現中期計画の最終年度かつ次期中期計画に向けた準備の1年です。役員報酬体系の再設計の議論もスタートします。外部環境が大きく変化する中、ボード全体として知見を高め、グループのさらなる成長をサポートしてまいります。

篠田:私は社外取締役であると同時に、常勤の監査等委員でもあります。グループ各社の監査役や内部監査部門、さらには当社のほかのボードメンバーとの連携を深めつつ、全社のガバナンス強化に貢献してまいります。
小宮:会計・財務知識の絶えざるアップデートに努めるとともに、ビジネスに関する知見を深め、より精度の高い監査でグループに貢献してまいります。
川名:バンダイナムコの最大の特徴は、IPを基軸とした事業展開です。強力な自社IPに加え、IPをともに育む能力、豊富なIPの出口戦略を擁しています。グループがこうした強みを十分に発揮し、真のグローバル企業として羽ばたいていけるよう、監督と助言の両面でサポートしてまいります。


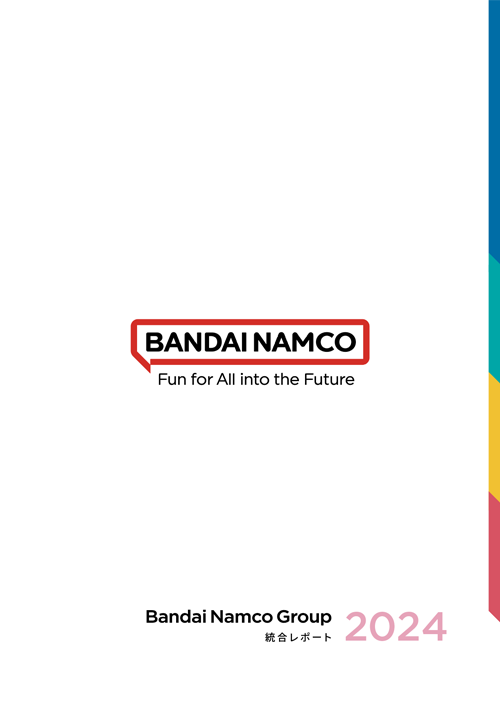
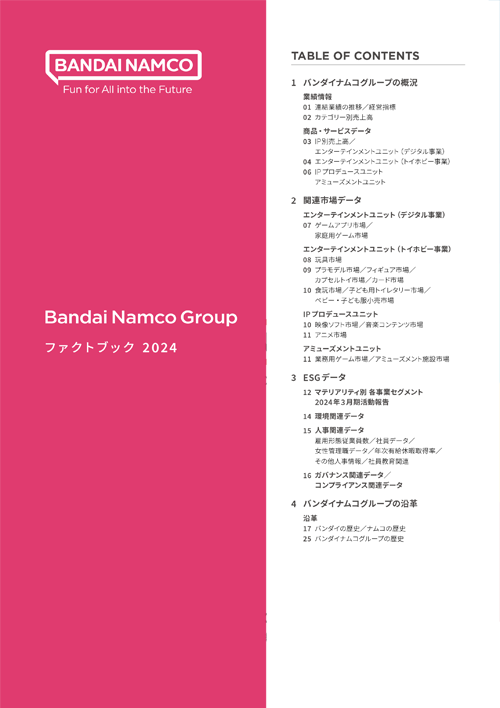

 MESSAGE
MESSAGE 統合レポート(日本語版)
統合レポート(日本語版) 10.5 MB
10.5 MB 多彩な事業領域
多彩な事業領域