

 独立社外取締役からのメッセージ
独立社外取締役からのメッセージ
パーパスの精神を踏まえ、
対話による協同・共創の経営に
貢献していきます。
 取締役会実効性評価のアンケート改訂
取締役会実効性評価のアンケート改訂
近年、企業経営に求められるテーマとして、資本収益性や人的資本、サステナビリティなどが注目されています。一方で、コーポレートガバナンス・コードの改訂動向は、取締役会における「個」の実効性を厳しく問うものとなっています。こうした状況のもと、当社取締役会は、さらなるガバナンスの改善に向けた検討を進めています。
その一環として先般、取締役会の実効性評価における質問票に手直しを加えました。取締役会の機能・機能を支える基盤・取締役の実効性という建て付けのもと、自己評価や相互評価を含む幅広い質問項目を準備し、この質問票により全取締役へのアンケートを実施しました。
独立役員会ではアンケート結果から認識された課題に対して、資本収益性や人的資本に関する ①今年度(2025年3月期)の取締役会やVision Meetingでの議論、②来年度以降の年間アジェンダ採択に向けた議論、などを提言しました。執行側のフィードバックを踏まえ、さらに議論を深めていく方針です。
取締役会評価は、評点の高さ低さだけにとらわれず、実態(項目ごとの評点)を認識し、当社の企業価値向上に向けての改善について、執行側と課題意識を共有し、改革への取り組みを進めていく流れにつなげる起点としていきます。
 スキルマトリクスの将来的見直しへ
スキルマトリクスの将来的見直しへ
当社を含め、多くの日本企業がスキルマトリクスを開示しています。ただ、その様式は会社によりまちまちです。そのこと自体は問題ないものの、評価項目の設定は恣意性を排した、客観的フレームに基づくものでなければなりません。スキルマトリクスの改善と活用は、前述のアンケートと同様に実施すべきことと捉えています。
当社グループでは、持株会社(当社)の社内取締役の多くが、事業統括会社の代表者を兼務しています。議論が分かれるところですが、これら事業統括会社にスキルマトリクスの導入と活用を進めることも、今後の検討テーマだと思います。グループガバナンスの強化、人材登用のストーリーが生まれ、スキルマトリクスと役員人事が連動し、有機的なピラミッドの構築につながるのでは、という考えが、当社の躍動的な価値と親和するかどうかなども議論をしていければと思っています。
 スキルマトリクスと新たな後継者育成
スキルマトリクスと新たな後継者育成
社長・役員の後継者育成(サクセッションプラン)とは、スキルマトリクスに規定された人材をどう育てていくか、という問題そのものです。ここでいう「スキル」とは、人を動かし業績を上げる力を含む、より広義の概念です。一般に企業の昇進人事には、現役職での実績を重視する「卒業方式」、上位の役職に必要なスキル習得を重視する「入学方式」の2つの考え方があります。当社も含め多くの日本企業では従来、前者が一般的でした。ただ、スキルマトリクスの整備が進めば、後者への転換も見えてくるかもしれません。
次世代のグループを担う経営者育成は、人事報酬委員会を中心にグループ全体のプログラム設計とモニタリングが進められています。従来は次世代までを育成対象としていましたが、さらにその次の世代まで育成対象を広げました。リスク管理の観点から、あえて事業環境の急激な悪化という“有事”に備え、少しでも多くの人材プールを確保しようという施策です。
 好調な時こそ、危機感とスピード感で対処
好調な時こそ、危機感とスピード感で対処
当社取締役会は、議長を務める川口社長が進行役・聞き役に徹し、誰もが率直に発言しやすい空気が生み出されています。ただ、私たち社外取締役と対照的に、社内取締役の発言はそれほど多くありません。各自がユニットの代表者だけに、他領域のことには口を出しづらい側面や、別の社内会議体で議論をしているということもあるのでしょう。中長期の課題を議論するVision Meetingは、双方向の意見交換の場としても活用されています。
社内取締役に新たな視点や気づきを与えるためには、私たち自身が絶えず研鑽を積まねばなりません。私は年に6~7回、出前授業で中高生たちと接する機会があり、顧客である彼らの“タイパ”(タイムパフォーマンス:時間対効果)重視の文化に強い衝撃を受けました。こうした経験からの学びは、次期中期計画に向けた議論にも活かしていくつもりです。
当社グループは近年、驚くべき急成長を遂げました。だからこそ、ここからが重要です。成功体験への固執は、往々にして転落の遠因となります。2023年に開示したいくつかの不祥事に対しては、その後の対応は適切になされましたが、好調な時だからこそ、今後はより危機感とスピード感を持って課題に対処していく必要があります。
 協同・共創の経営へ
協同・共創の経営へ
 バンダイナムコの強さを支える最大の原動力は、「ファンとつながり、ともに創る」パーパスの精神です。当社の株主の中にも商品・サービスのファンである方が多くいらっしゃいますが、その方々との一体化が生み出す熱量の大きさは、株主総会などで常々実感しています。この熱量が企業価値の向上にそのまま結びつくよう適切な施策が取られているか、短期の数字に気を取られてこの原点を見失っていないか、それを見定めることも社外取締役の役目の1つです。ニーズの多様化や環境変化を長期視点でどう捉えるか、という問題もここに含まれます。そしてこうした点につき、私たちは皆様からの多様なご意見をお待ちしています。
バンダイナムコの強さを支える最大の原動力は、「ファンとつながり、ともに創る」パーパスの精神です。当社の株主の中にも商品・サービスのファンである方が多くいらっしゃいますが、その方々との一体化が生み出す熱量の大きさは、株主総会などで常々実感しています。この熱量が企業価値の向上にそのまま結びつくよう適切な施策が取られているか、短期の数字に気を取られてこの原点を見失っていないか、それを見定めることも社外取締役の役目の1つです。ニーズの多様化や環境変化を長期視点でどう捉えるか、という問題もここに含まれます。そしてこうした点につき、私たちは皆様からの多様なご意見をお待ちしています。
機関投資家などと独立社外取締役、両者が建設的な目的を持って対話し、相互理解を深めることで、企業価値向上への道につながる、という意見には賛同します。皆様が見ておられるもの、私たちが見えていないものを、その逆も含め、ともに学びつつ議論し、協同・共創の関係を築いていければ、多様なステークホルダーの期待に応える経営に深化していくのだろうと考えています。



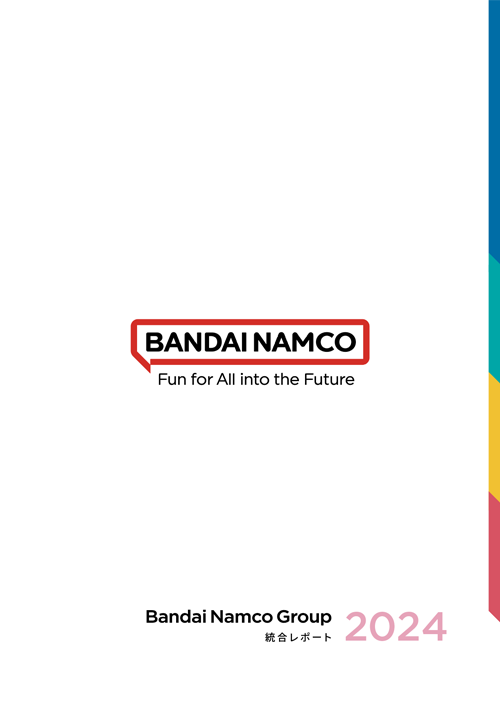
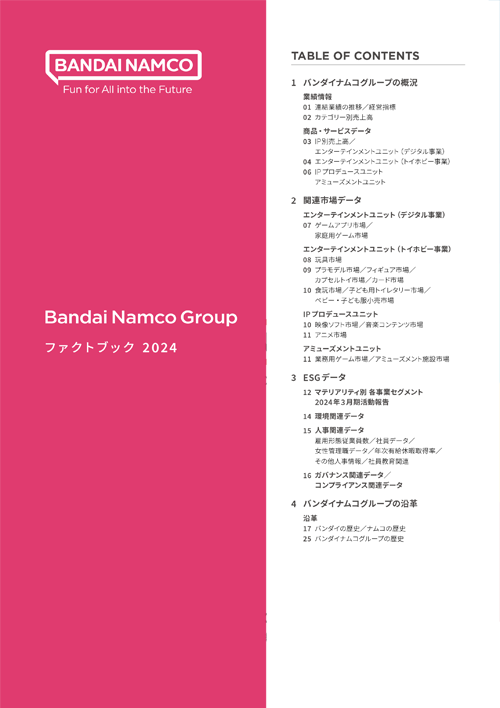

 MESSAGE
MESSAGE 統合レポート(日本語版)
統合レポート(日本語版) 10.5 MB
10.5 MB 多彩な事業領域
多彩な事業領域