

 社外取締役座談会
社外取締役座談会
新たなステージでの持続的成長を後押ししていきます。
新たな経営チーム体制のもと、中期計画がスタートしました。
「バンダイナムコらしさ」にこだわりながら、
当社グループのガバナンス向上を目指す社外取締役5名が忌憚のない意見交換を行いました。
 島田 俊夫
社外取締役
島田 俊夫
社外取締役
 川名 浩一
社外取締役
川名 浩一
社外取締役
 篠田 徹
社外取締役 監査等委員
篠田 徹
社外取締役 監査等委員
 桑原 聡子
社外取締役 監査等委員
桑原 聡子
社外取締役 監査等委員
 小宮 孝之
社外取締役 監査等委員
小宮 孝之
社外取締役 監査等委員
 2025年3月期業績の評価
2025年3月期業績の評価
島田:2025年3月期(以下、当期)の当社は素晴らしい業績でした。一方、あえて言うならば、当初計画数値からの上振れが、少々気になる部分です。業績予想があまりに保守的と受け取られるのも、投資家とのコミュニケーション上、課題となります。また、ボラティリティの高いデジタル事業が、開発体制の見直しで、どのように変わっていくかも、注視する必要があります。
川名:全体業績もさることながら、すべてのセグメントが増収増益となり、全体的な底上げや事業間連携ができてきました。成長に向け各事業部門で打ってきた様々な施策が芽吹いてきた状況と受け止めています。デジタル事業についても、投資を含めた開発体制の見直しといった、一連の改革の成果が少しずつ出てきたように思います。
篠田:近年の急成長を支えているのは、多彩な事業ポートフォリオです。ファンにとって価値ある商材の提供に向け、グループの総合力を発揮することで、安定的な収益基盤が構築されてきました。デジタル事業の改革については、強みを発揮できる分野で成功確度の高いゲームづくりを目指す方向性は概ね妥当ながら、今後は、全く新しい分野へのチャレンジにも期待しています。
桑原:トイホビー事業が7期連続で過去最高業績を更新したことを含め前中期計画の最終年度を最高の形で締めくくったこと、また、過去の中期計画と比べ、営業利益の水準が底上げされてきたことを評価しています。デジタル事業では、タイトルポートフォリオ管理に基づいた戦略性が向上してきました。一方で、ゲーム開発特有のリードタイムの長さから、改革の本当の効果が表れるのはもう少し先になるでしょうし、こうした手法と創造性の両立についても、しっかり見ていきたいと思います。
小宮:全面的な増収増益、また10年以上におよぶ、ほぼ右肩上がりの成長は、素晴らしいと思います。デジタル事業についても、案件規模を意識した開発スケジュールや投資のコントロール、類似案件の実績に基づく将来予測など、開発期間の長期化・コスト増を踏まえた構造転換が着実に進捗していると見ています。
 中期計画と長期のビジョン
中期計画と長期のビジョン
島田:今回の中長期ビジョンは、前中期計画の中期ビジョンを進化・拡充しましたが、さらに長期のビジョンをどうするのか、という課題があります。現状は足元への対応の連続が結果として中長期につながっていますが、資本市場との対話や、将来の大きな環境変化に備える観点で、目指す未来像からのバックキャストという方式を検討する価値があるでしょう。不透明な時代状況や、事業ごとのライフサイクルの違いなどにも留意しつつ、議論を一層深めていきたいと思います。
川名:当社グループの手掛けるIPやアニメ・ゲームの輸出は、日本発の価値創造をグローバルに具現化する取り組みです。それは、日本の国際的魅力を高め、ひいては国益にも貢献しています。従業員の皆さんにはぜひ、そうした誇りを胸に仕事に臨んでいただきたいし、そこで長期ビジョンの果たす役割は大きいだろうと考えています。
篠田:パーパス策定に際し、Vision Meetingや役員合宿などで、10年後のありたい姿をテーマに議論を重ねました。グループ全体の長期の方向性を展望することは、確かに重要でしょう。一方で、長期にまたがる事柄は、一概に決められるものでもありません。むしろ、長期の問題意識を中期計画に落とし込み、それを積み重ねていくべきではないでしょうか。
桑原:今回は、今中期計画の策定に向けての議論が中心になりましたが、その中でも例えば、“360”投資やサステナビリティの考え方には、より長期の視点が含まれています。こうした議論の積み重ねが、その先の長期ビジョンにつながっていくことを期待しています。

資本市場との対話や、将来の大きな
環境変化に備える観点で、目指す未来像からの
バックキャストという方式を検討する
価値があるでしょう。
 グローバルなリスク管理
グローバルなリスク管理
島田:当社グループを取り巻く課題/リスクは、制御不能な地政学的要因を除くと、①海外マネジメント人材の確保、②コーポレート機能の強化、③AIの進化、④情報セキュリティの4つに大別できるでしょう。このうち①と②は、急成長する事業を支えていくうえで急務です。③のAIは、今後3年間で大きく進化し、新たな市場を形成する可能性があります。最後に④に関しては、グループ全社員の意識の底上げに向け、経営陣や部門長レベルからの発信強化が求められます。明日、何が起きるか分からないという緊張感を持って、事前の防止策・事後の対処法を、常に意識の片隅に置くことが大切です。
川名:挑戦にはリスクが付き物で、私たちはむしろ適切なリスク管理を前提に、執行側を後押ししていく姿勢を持つべきでしょう。そのためにも重要なのはリスクに対する認識とそれらの特定であり、当社ではグループリスクマネジメント委員会を通じ、その発生頻度や危険性の把握に努めています。また、想定外の事態発生に備え、日頃から複数のプランを議論しておく必要があるでしょう。これらすべての鍵を握るのは、我々社外役員を含む多様な人材による多様な視点や考え方です。
篠田:喫緊の課題は、コーポレート機能と情報セキュリティの強化でしょう。特に海外拠点は、コーポレート機能が必ずしも盤石ではありません。そこで当期、監査等委員会では重要監査項目として情報セキュリティ対応の監査を実施しました。現地の体制拡充、継続的な監査などにより、危機感を持って対応を強化していきます。
桑原:グループ事業の急成長にコーポレート機能の強化が追い付いていない面が見受けられます。今後は特に海外拠点について、強い課題意識を持って臨んでいく必要があります。ローカルの体制強化に加え、グループとしてのグローバル人材育成も重要です。特に経営人材のローテーションについて、しっかり見ていきたいと思います。
小宮:不祥事の発生防止や事後対応は、企業文化にも大きく関わるテーマです。グローバルな拠点・人員の拡大に伴うリスクの増大、またSNSの普及などを背景としたレピュテーションリスクの問題を踏まえ、他社の事例も参照しながら、対策を強化する必要があります。
私たちはむしろ適切なリスク管理を前提に、
執行側を後押ししていく姿勢を
持つべきでしょう。

 新経営体制の始動
新経営体制の始動
島田:浅古社長の選任プロセスにおいては、人事報酬委員会(以下、委員会)としては執行側から提示された候補者案に対し、諮問を行いました。コーポレート機能の強化や資本市場を意識した経営を進めていくうえで、これまでの経歴から見ても、浅古取締役(当時)が適任という説明を受けました。その後、本人とも改めて面談した結果、委員会としても経営トップとして妥当な人選であると結論付けました。
川名:CEOの選解任はガバナンスの一丁目一番地です。私たちは委員会の場で、執行側と様々な意見交換を行いました。資本戦略に裏打ちされた新たなバンダイナムコの成長戦略を描くには、浅古取締役が適任である。併せて、ビジネスの現場を熟知し、海外経験も豊富な桃井取締役に、副社長として事業戦略を任せたいという話を踏まえ両氏と面談を重ねた末、この経営陣にグループの将来を託すとともに、背後からサポートしていくことが最善であるという想いに至りました。
桑原:執行側に提案理由や基本的な考え方について説明を求め、実際に面談も重ねたうえで、納得して結論を出しました。浅古社長はコーポレート部門出身で、財務のみならず投資家との対話やM&A戦略などでも、リーダーシップを発揮してきました。一方、桃井副社長は、ユニットの垣根を越え、グループ横断的な立場から、国内外のビジネス全般を見てきました。このタイミングでのお二方の社長・副社長就任は、大変良かったと思います。
島田:自分で事業ユニットを率いる人は、立場上、そのビジネスの最適化を重視します。広くマーケットと未来を展望し、現場の課題も熟知している桃井副社長と、バックオフィスに強い浅古社長が連携することで、素晴らしいチームが形成されるでしょう。
川名:桃井副社長は個性豊かな人物で、コミュニケーション力も高く、情熱と行動力を備えています。バンダイナムコの情熱を世界中に広げていくエバンジェリスト、あるいは未開の荒野を切り拓く強力なブルドーザーとしての活躍を期待しています。

一概に決められるものでもありません。
むしろ、長期の問題意識を中期計画に
落とし込み、それを積み重ねていくべき
ではないでしょうか。
 取締役会の多様性向上へ
取締役会の多様性向上へ
桑原:新任取締役のお二方についても、選任プロセスは同様です。辻取締役CFOには、私自身も取締役会関連の様々なサポートを受けてきており、その人となりはよく理解しています。また藤田取締役は、コーポレート機能の強化という大きな目的に対し、適切な人材が選ばれたと評価しています。
川名:辻取締役CFOとは、以前から何度も話す機会がありましたが、安定感があり、信頼できる人物です。藤田取締役についても、社内の評価が高く、真面目な実務家という印象を持っています。
委員会ではこのほか、各事業会社の新任取締役とも面談していますが、ユニークで魅力的な人が多く、このグループは人材の宝庫だなと感じます。「同魂異才」を掲げるバンダイナムコの真骨頂とも言えるでしょう。
島田:藤田取締役には、次々世代の育成プログラムで何度かお会いし、バンダイの取締役になられた際にも面談しており、今後のさらなる活躍を期待しています。取締役会の人的多様性を高める観点からも、今回の人選は全般的に評価できると思います。
篠田:私も、グループの持続的な成長に向けて基盤を強化する今中期計画を推進するうえで、新任取締役含めて最適な体制であると感じています。
桑原:宇田川取締役に続く社内2人目の女性取締役誕生は、大変良かったと思います。お二方とも、実力が評価されて上がってきた人たちで、今後の女性活躍に向け、力強いメッセージになったはずです。
後継者育成計画(サクセッションプラン)については、候補者を3階層に分け世代別に経営人材の育成を続けています。委員会では毎年、その進捗状況について報告を受け、議論を続けていますが、人材は年々豊富になり、また下位の層に行くほど女性比率が上がるなど、着実な手応えを感じます。
島田:もし長期ビジョンの議論にめどが付けば、人材要件についてもバックキャストの手法が使えるようになります。将来、求められる人材像は今とは異なる可能性がありますし、取締役会全体の構成を見直す必要が出てくるかもしれません。
 役員報酬制度見直しの着眼点
役員報酬制度見直しの着眼点
島田:役員報酬制度に関しては、変動報酬のKPIとして、従来の連結営業利益に加え、株価と連動した新たな財務指標の採用をかねてより検討していました。私自身のイメージは、株価と完全に一体の時価総額でしたが、このほど1株当たり当期純利益(EPS)の採用で決着しました。EPSは、株価との連動性が高く、まずは大きな前進と言えるでしょう。
また、サステナビリティ評価については、評価項目を脱炭素と従業員エンゲージメントの2つに絞り込みました。導入3年目となる当期の評価スコアは、ニュートラルでした。
川名:もともとサステナビリティ評価のスコアは、弾力的に変動しにくい性質があります。導入2年目(2024年3月期)は、取り組み体制の整備を評価して1段階引き上げましたが、3年目の当期は、いわば実行段階の初年度として、改めてニュートラルに戻したわけです。
桑原:サステナビリティ評価は、導入そのものがメッセージ性を持つ重要な指標ですが、運用面では、評価項目が多くなるため、結果として全体ではニュートラルになりやすいという問題がありました。そこで、指標としての実効性を高め、よりメリハリを付けるべく、評価項目を整理しました。
財務のKPIについては、株式市場を意識した指標として、例えばTSR(株主総利回り)を採用する会社もありますが、その場合、マーケットとの比較といった相対的な要素も出てくるため、より直接的なEPS評価を選択しました。EPSが指標に加われば、自己株式の取得を含め、株主還元の在り方を意識せざるを得なくなるという意味で、良い着眼点だと考えています。
自己株式の取得を含め、
株主還元の在り方を意識せざるを
得なくなるという意味で、
良い着眼点だと考えています。

 社外取締役に求められるもの
社外取締役に求められるもの
島田:社外取締役への社会的要請が高まる中、自分自身はどうあるべきか、絶えず自問自答しています。私の考えでは、社外取締役に求められるのは、「良い問いかけ」を発する能力です。私は取締役会の場で、議案に対する忌憚のない感想、別の視点からの意見を、意識して述べるようにしています。執行側がハッとするような問いかけを少しでも多く発することで、「投資家の代理人」たる社外取締役の責務を果たしていきたいと思います。
川名:取締役会が会議体として健全に成長し、適切にガバナンス機能を発揮できるよう支えていくのが、社外取締役の役割です。私たちは自分自身で何かを行うわけではなく、あくまで執行側に働きかけ、「気づき」を促す存在です。そのためには、異業種の世界で生きてきたからこそ感じる、ふとした違和感を大切に、発言すべきことはいつでも、空気を読まずに言い切る。それを許す自由な空間である当社取締役会のさらなる成長に向け、等身大の自分で貢献していきたいと考えています。
篠田:安定的な収益基盤の構築を重視する立場から、取締役会においては、審議事項の大前提となるコーポレート機能に着目し、様々な発言を行っています。また監査等委員会では、情報セキュリティ監査を精力的に実施しています。一方で、こうしたアプローチが、バンダイナムコならではの自由なチャレンジを阻害しないか、両者の最適なバランスはどこにあるのか、というのは難しいテーマです。私自身、その答えを持っているわけではありませんが、執行側がこの問題をどう捉えているかを常に注視し、監査の糸口にしていきたいと思います。
桑原:バンダイナムコらしさの理解・尊重と、マーケットの要請とは、時に相反する関係にあります。そして、これら両者の間に割って入ることができるのが、社外取締役でしょう。「バンダイナムコらしさだから、これで良いんだ」という思考停止を排し、議論をさらに一歩深めつつ、皆様とともにベストプラクティスを追求していきたいと考えています。また監査等委員としては、アクセスできる情報量の多さを活かして、何か気になることがあれば、早期の段階で執行側に提言し、体制整備のきっかけづくりに貢献していきたいと思います。
小宮:私自身の業界他社での経験からいって、当社グループのガバナンスは、一般的なエンターテインメント企業に比べ、相当に高い水準にあると感じています。これは、浅古社長のこれまでのリーダーシップに起因するものかもしれません。いずれにせよ、この優位性に磨きをかけるべく、フロント/バックオフィスをバランス良く鍛え、バンダイナムコをより強い会社に成長させていきたいと思います。

フロント/バックオフィスを
バランス良く鍛え、
バンダイナムコをより強い会社に
成長させていきたいと思います。
私にとってのパーパス
島田すべてはファンが楽しく、笑顔でありつづけるサービスを提供し続けていく想いが込められたパーパスだと考えています。
川名パーパスが示す「人と人、人と社会、人と世界がつながる」世界が来ることを願っています。その世界の実現にバンダイナムコが貢献し、輝く存在となることを期待しています。
篠田「夢・遊び・感動」を追求することで人々とつながり、ともに創っていく。生活必需品でないからこそ提供できるエンターテインメントの価値のポテンシャルの高さを端的に表したパーパスだと考えています。
桑原グローバルな分断が進む時代だからこそ、エンターテインメントの力で笑顔溢れる未来をつくることの重要性が表れているパーパスだと捉えています。
小宮パーパス実現のため、ファンの期待に応えることが重要です。そのためには、期待がどこにあるのかを探求し、応えていく必要があると考えています。



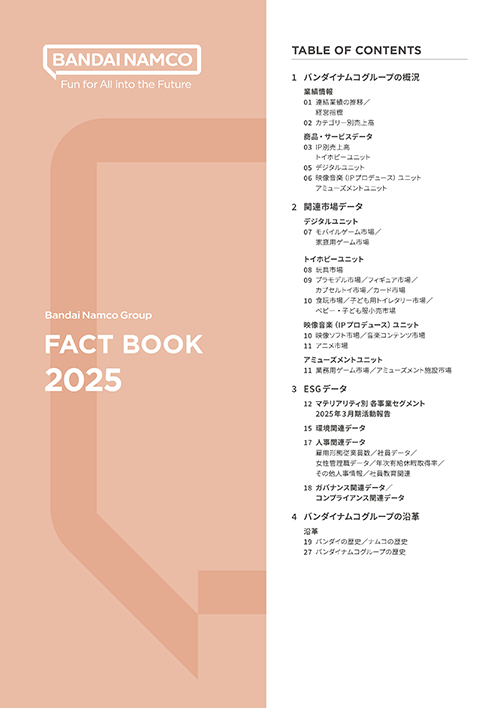

 会長メッセージ/社長メッセージ
会長メッセージ/社長メッセージ 統合レポート(日本語版)
統合レポート(日本語版) 17.6 MB
17.6 MB IPラインナップ
IPラインナップ